こんにちは。らどゆきです。
医療従事者の皆様、研究についてどのような印象をお持ちでしょうか?
・臨床だけで精一杯!
・研究なんて意味ない!
・お金もらえないからしない!
このような声をよく耳にします。
確かに、このような側面があるのも事実です。
この記事では、研究で論文を多数輩出している著者が研究の良いことや問題点を解説します。
- 上司に言われて「やりたくないなぁ…」と思いつつ研究している方
- 「研究に興味はあるけど、よくわからない」と思っている方
- 医療と無縁だけどなんとなく興味のある方
著者(らどゆき)についても紹介させてください。
この記事を読んでいただくことで次のことを理解できます。
- 研究者がなぜ研究をするのか
- 研究の良し悪し
- 私 (らどゆき) が研究してて良かったこと
- 研究がお金を稼ぐことにつながった理由

自己開示も含め、雑談的な内容として読んでいただけると嬉しいです!
研究は新しいことを発見すること

そもそも研究って何をするのか。
ChatGPTに聞いてみました。
研究とは、既存の知識や技術を深めたり、新しい発見や発明を行ったりするための体系的な探求活動です。大学や研究機関、企業などで行われることが多く、自然科学、人文科学、社会科学など、さまざまな分野で展開されています。
色々書いていますが、まとめると
新しいことを発見し、患者さんの利益につなげること
です。
ざっくりですが、医療の分野では
- コロナ患者さんにはどんな薬が効くのか
- AIを使って診断精度を向上できないか
- 看護師による患者さんにベストな退院支援
- CT検査でより放射線被ばくを減らせないか
なんてことを研究しています。

研究で患者さんの治療や健康増進に役立つヒントを得ることで、最終的に患者さんに恩恵をもたらすことが最終的なゴールです。
研究のメリット3選

この項目では、研究するメリットを3つ紹介します。
診療する患者さん以上の人の役に立てる
病院で診療する場合、自分が役立てるのは目の前の患者さんに対してだけです。
しかし研究して論文にすることで、より多くの人の役に立てます。
私の場合、一日にCTを撮影する患者さんは50人程度です。
一年で200日働くとして、私の影響範囲は1万人。
でも英語で論文を書いた場合、対象者は最大80億人です。
文字通り桁違い。
自分の研究が80億人の役に立つかもしれないんです。
激熱じゃないですか?
自分に付加価値を付けることができる
研究していることで自分自身に付加価値を付けれるようになります。
一部のスーパードクターを除いて、
・ある程度マニュアルを整備して
・数年間適切に教育すれば
極端な話、臨床はある程度誰でも同じようなことができるようになります。
でも研究は違います。
・論文という明確な実績
・研究で培った論理的思考能力
・壁にぶつかったときの問題解決能力
これらは、研究を継続することで獲得できる恩恵です。
(これらは副業に活きました!)
研究をすることで、その他大勢のスタッフとの差別化が可能です。
・院内で同僚からの信頼を得られ働きやすくなる
・上司から評価される
・転職時のアピールポイントになる
研究をすることで、これらの付加価値をもたらしてくれます。

余談ですが、私は研究で成果を出してから職場で意見が通りやすくなったような気がします。
知的好奇心が満たされる
研究は、知的好奇心を満たし、仕事へのモチベーションを上げてくれます。
- 課題と思えるテーマを自分で探索し
- 未知な疑問を解決する
- そして新しくなった知識を他の研究にも活用してもらえる
純粋に新しいことを知るのも楽しいですし、他の人の研究のヒントになるのも嬉しいです。
研究のデメリット3選

この項目では、研究のデメリットを3つ紹介します。
多大な時間を使う
研究には多くの時間が必要です。
・先行研究の調査
・研究計画の立案
・データ収集
・解析
・論文執筆
など、全体的に手間がかかります。
加えて、患者さんのデータを使用する場合には、倫理的配慮が問題ないかを審査してもらうことが必要です(倫理審査)。
この手続きに数か月を要します。
慣れていくことで時短術は身につきます。
施設や職種によっては、業務時間内に研究時間を確保できるようです。
ですが、少なからず自分の時間を使わざるを得ないことも事実です。
成果を出してもお金を稼げない
研究で成果を出しても収入が増えるとは限りません。
職場から研究成果に対する手当てが出るかは病院次第です。
私の病院では成果を出しても手当をもらえません。
時間を使って成果を出してもお金をもらうことができないんです。

「拷問かな?」と思っている時期が私にもありました。
研究にもお金がかかる
お金を稼げないだけではありません。
研究費を取得できなければ、研究費用は自費なんです。
・研究ツール(PC、解析ソフトなど)
・学会参加費
・英文校正費用(ネイティブに英語をチェックしてもらうこと)
など、多くのコストがかかります。
特に海外学会への参加となると、旅費や宿泊費が数十万円の負担となります。
研究費を確保できていない、職場から支給がない場合、金銭的なハードルが高すぎますよね。

「拷問かな?」と思っている~略
研究を続けてよかったこと3選

ここまで読んでくださったあなた。
研究なんかせんわ!!!!!
と思いましたね?(笑)
この項目では、私が研究を続けてよかったと感じたことを3つ紹介します。
論文が受理された達成感
長い時間をかけて行った研究成果を論文にまとめ、学術雑誌に受理されたときの達成感は格別です。
特に厳しい査読を通過して掲載された場合、その喜びは何物にも代えがたい喜びがあります。
※査読:研究で得られた知見や研究アプローチを審査されること
論文受理のメールを受け取る瞬間、脳汁がドバドバになります。
この達成感が、次の研究へのモチベーションです。
周囲に一目置かれる
研究を続けて成果を上げることで、職場や学会での評価が高まります。
周囲から一目置かれる存在になること間違いなしです。
論文はそのくらいのインパクトがあります。
また、研究者としての経験がキャリアアップにもつながることがあります。

数年前、ある学会で国内第一人者の先生に
「君の論文読んでるよ」
と言ってもらったことを今でも鮮明に覚えています。
学会中に少しだけ観光できる
学会発表は、研究成果を広める重要な場です。
時期によって東京や北海道など、さまざまな場所で開催されます。
そのため、学会の合間に観光することも可能です。
観光は研究活動の隠れた楽しみの一つです。

私は福岡在住なので、横浜や大阪の学会に参加するときにはテンション上がります。
ぶっちゃけ、学会直前は発表内容よりもどこに行くか考えてるまであります(笑)
研究をしたことでwebライターとして稼げた話

最後に、お金を稼ぐ力に関する紹介です。
Webライティングをはじめ、2か月で月5万円稼ぐことに成功しました。
研究の経験がwebライターとしてどのように活用されたのかを解説していきます。
きちんとした文章を書けていた
研究活動を通じて培った文章の執筆のスキルがwebライティングに役立ちました。
科学論文とweb記事の書き方は若干異なることは事実です。
ですが、書籍で学び、書き方をフィッティングすることである程度適用できたように思います。
読みやすく、正確で、論理的な文章を書く能力は、webライターに求められるドンピシャのスキルです。

研究活動で文章を多く書いていた経験が活きていると常々実感していました!
根拠に基づいて記事を執筆できた
医学系の記事を執筆する際には特に正確性が重視されます。
正確性を担保するためには、文献(論文やガイドライン)を検索し読み解くスキルが必要です。
これまでの研究活動で文献を検索してきた経験をwebライティングに活かすことができました!
新米webライターでも文字単価2円で継続案件をいただけた
研究経験を活かした結果、医療記事を執筆する案件を獲得できました。
新米ライターでありながら文字単価2円で10件以上の案件をいただけました。
これにより、月5万円を達成できたといっても過言ではありません。
まとめ:研究で培った能力は副業にもいきる
研究活動には多くの時間と労力が必要です。
必ずしもお金を稼げるわけではありません。
しかし、その過程で得られる知識やスキルは、他の分野でも十分に活かすことができます。
私のwebライターとしての活動では、研究経験が大きな強みとなり、
比較的高単価案件を獲得するきっかけにもなりました。
研究を通じて培った能力を活用することで、お金を稼ぐことも夢ではありません。

本記事がこれから研究を始めるあなたの参考になれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
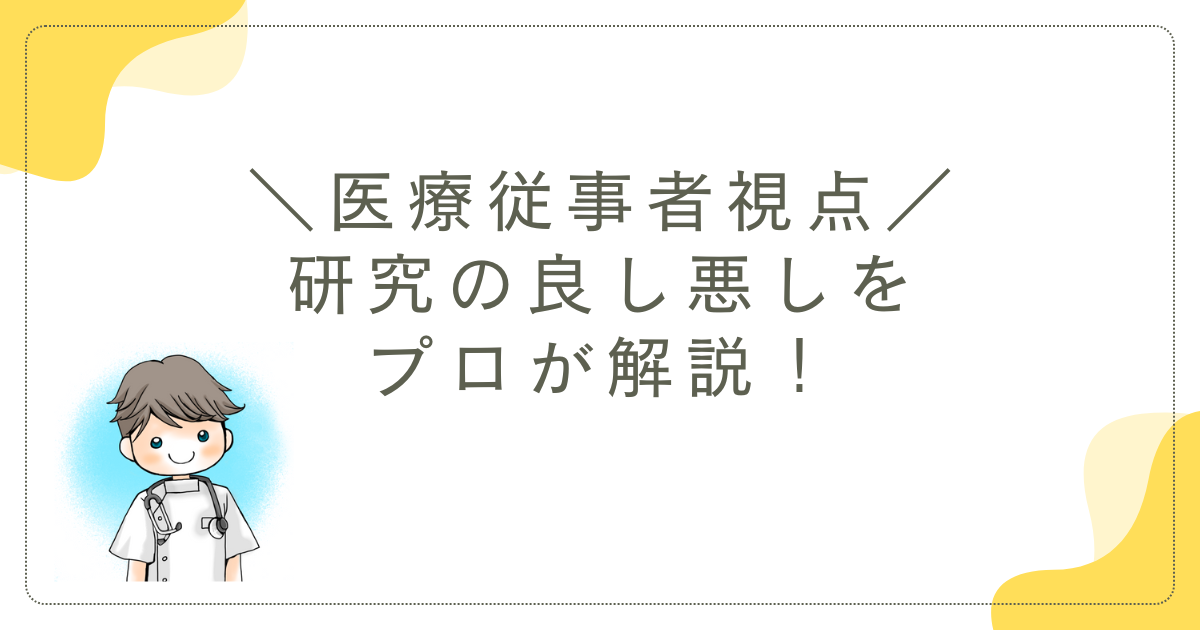


コメント